大人の発達障害を知る感覚過敏・感覚鈍麻
とは
それぞれの特徴と発達障害との関連性、
対処法を紹介

小さい音でも大きく感じる、どうしても苦手な匂い・肌ざわりがある、または痛みを感じにくいなど、感覚に関する困りごとはありませんか。それは感覚過敏・感覚鈍麻とよばれるもので、ときには生活の中で大きなストレスとなることもあります。
それぞれの特徴や対処法、体験談などを紹介します。
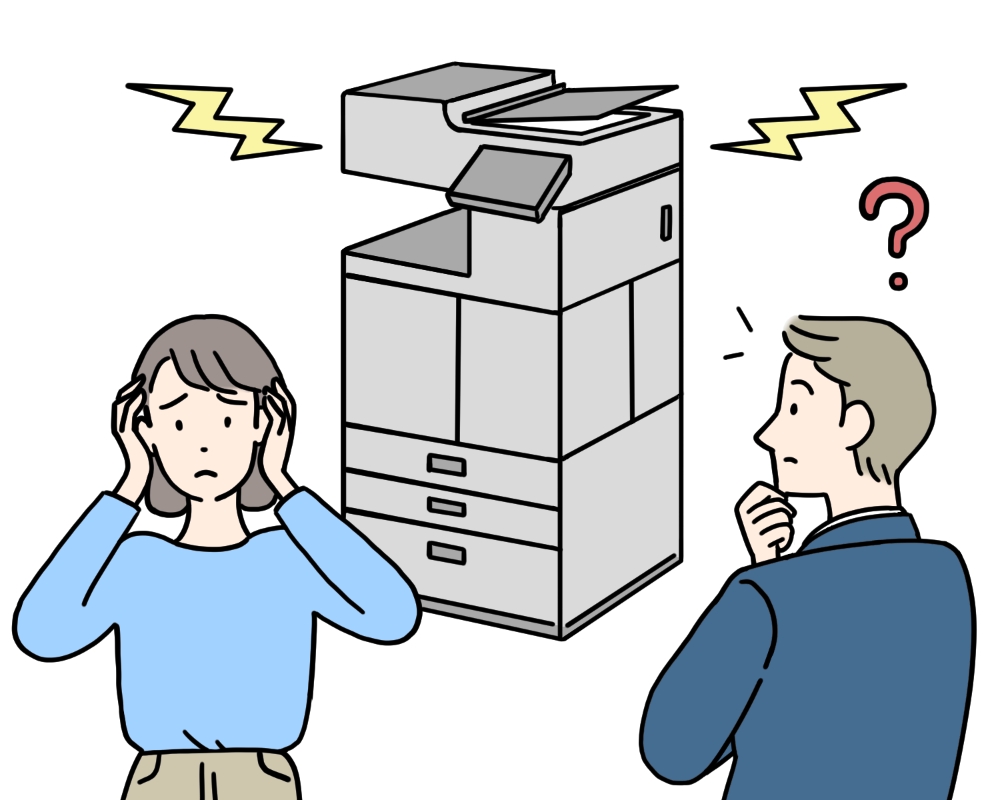
感覚過敏・感覚鈍麻とは
騒がしい場所でとても不快になったり、衣類の肌ざわりが気になったり、強烈に好きな触感や匂いがあったり、または刺激に対して他の人と同じような反応が起こらなかったり――
このような状態は感覚過敏または感覚鈍麻という「感覚に対する脳の偏り」などが原因で生じる反応です。主に五感(視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚)や固定感覚、平衡感覚などの感覚が過剰に反応する場合を感覚過敏、反応が鈍い場合を感覚鈍麻とよびます。
これらの反応自体は病気としては扱われませんが、日常生活に支障が出るほどつらいと感じるのであれば、医療機関や支援機関に相談したりサポートを受けたりしたほうがよいでしょう。
感覚過敏・感覚鈍麻の原因
感覚過敏・感覚鈍麻の状態が起こる原因として、以下のようなことが考えられています。
- 感覚に対する脳の偏り:五感への刺激に対し、何らかの要因から脳がうまく機能せず、刺激へ過剰に反応したり、反応しなくなったりする。
- 感覚受容器の病気:目や耳、鼻などに病気があることで感覚に異常が生じる。突発性難聴やメニエール病など。
※感覚受容器:目や耳、鼻など刺激などの情報を感知する受容器の総称
- ストレス:ストレスを抱えている状況から、身体症状として感覚過敏・鈍麻が現れることがある。
発達障害との関連性
ADHDやASDの特性がある人では、感覚過敏・鈍麻を併せ持つことが多いとされており、ASDの特性がある人でその割合はより高いといわれています。DSM-5-TR(米国精神医学会が作成する「精神疾患の診断・統計マニュアル」第5版の2022年本文改定版)では、発達障害の特性の一つとして感覚過敏・鈍麻のような感覚異常があると記載されています。ただし、発達特性のある人すべてに感覚過敏・鈍麻があるというわけではありません。
感覚過敏・感覚鈍麻の症状と対処法
ここでは、五感における感覚過敏の症状と対処法を紹介します。
なお、各症状に共通する対策として、無理に我慢せず、苦痛を軽減する対処法を身につけることが重要です。
感覚過敏
<視覚過敏>
- よくある
症状 -
- 日光や室内光、パソコン画面などの光がとてもまぶしく感じ、目を開けていられなかったり、気分が悪くなったりすることがある
- 少しの明かりでもまぶしく感じて、夜眠れない
- テレビや情報端末などからの視覚的な情報量がとても多く感じて、混乱する
- 特定の色や柄が苦手
- 対処法
-
- 屋外ではサングラスや帽子など、光のまぶしさから目を守るアイテムを着用する
- 室内では蛍光灯を使用しない、あるいは明るさ抑えて間接照明を併用する。朝の日光がまぶしい場合は遮光カーテンを使用する
- テレビやパソコンからの刺激を抑えるために、ブルーライトカット機能のある眼鏡や音声読み上げ機能を使用する
- 苦手な色などを避け、周囲にも伝えて調整してもらう
<聴覚過敏>
- よくある
症状 -
- 大きな音、特に突然の音が苦手
- 小さな音でも大きく感じる、または周囲の音がすべて同じ音量で聞こえる
- 周りの音が騒がしいと人の話が聞き取れないときがある
- 時計の秒針の音やエアコンの動作音などの小さな生活音が気になる
- 特定の音(子どもの泣き声や騒音など)に耐えられない
- 対処法
-
- イヤーマフやヘッドホン、耳栓などを着用し、大きな音や雑音をシャットアウトする
- 苦手な音がする場所から離れたり、生活環境を調整したりする
聴覚過敏のある方の体験談はこちら
※当事者の方向けコンテンツです
<触覚過敏>
- よくある
症状 -
- 特定の感触が苦手
- 衣服の内側のタグや着心地、素材などが気になる
- 肌が濡れたり汚れたりすることを嫌う、髪をとかすことや歯磨きが苦手
- マスクを着用することができない
- 人に触れられることが苦手
- 対処法
-
- 好きな肌触りのものを常備しておく
- 衣服(肌着や下着も含め)は、タグを切ったり苦手ではない素材のものを購入したりするようにする
- 周囲にも伝え、理解してもらう
<味覚過敏>
- よくある
症状 -
- 特定または独特の食感が苦手、または味を強く感じる
- 匂いや味が混ざった食べ物が苦手
- 偏食や食べず嫌いがある
- 対処法
-
- 苦手なものは無理に食べず、調理方法や味付け、食べ方を変えるなどの工夫をしながら、栄養が偏らないように配慮する
- 味が混ざらないように盛り付ける
<嗅覚過敏>
- よくある
症状 -
- タバコ、化粧品、人や動物の匂いなど、特定の匂いが苦手で、ときには気分が悪くなることもある
- 動物園や化粧品売り場など、匂いを強く感じるために苦手な場所がある
- 人が気にならない匂いも気が付く
- 苦手な匂いを避けるために外出や人に会うことを避ける
- 対処法
-
- マスクを着用したりタオルで鼻を塞いだりする
- 好きな香りを身につけ、苦手な匂いを感じづらくさせる
感覚鈍麻
感覚鈍麻のよくある症状と対処法を紹介します
- よくある
症状 -
- 温度の変化に無頓着
- 音が聞き取りにくい、人に呼ばれても気が付かないことがある
- 痛みがあっても、気がつきにくい
- 味の変化を感じにくい
- 対処法
-
- 危険があるものに対して距離を取り、触ってはいけないものを分かりやすくしておく
感覚過敏・感覚鈍麻は何科に相談すればいい?
感覚過敏・感覚鈍麻の症状がある人や、実際に困りごとが生じている場合には、症状がある器官の専門医を受診するとよいでしょう。
ただし、発達障害に伴う感覚過敏、鈍麻は、身体的な検査で異常がみられないことが少なくありません。
視覚…眼科
聴覚…耳鼻咽喉科
触覚…皮膚科
味覚…耳鼻咽喉科、口腔外科
嗅覚…耳鼻咽喉科
また、発達障害について精神科や心療内科などの医療機関に通院している場合は、その主治医に相談することもできます。
感覚過敏・感覚鈍麻は、自身の症状を理解し工夫することで生活しやすくなるとともに、専門医でサポートを受けることもできます。それぞれに合った対策を考えていきましょう。
監修:昭和大学 発達障害医療研究所
所長(准教授) 太田晴久先生
本文中に使用されている専門用語(アンダーラインのついたもの)については発達障害関連ワード集に詳しく説明があります。
