発達障害との付き合い方ガイドブック発達障害との
付き合い方

発達障害とうまく付き合い、
自分らしく生きる
発達障害は生まれつきの脳の特性ですので、「治す」というよりも「対処する」や「付き合う」という表現の方が合っているとも言われています。
それぞれの特性にうまく対処していくことで、生きづらさをやわらげ自分らしい生活を送ることができます。

対処法の考え方
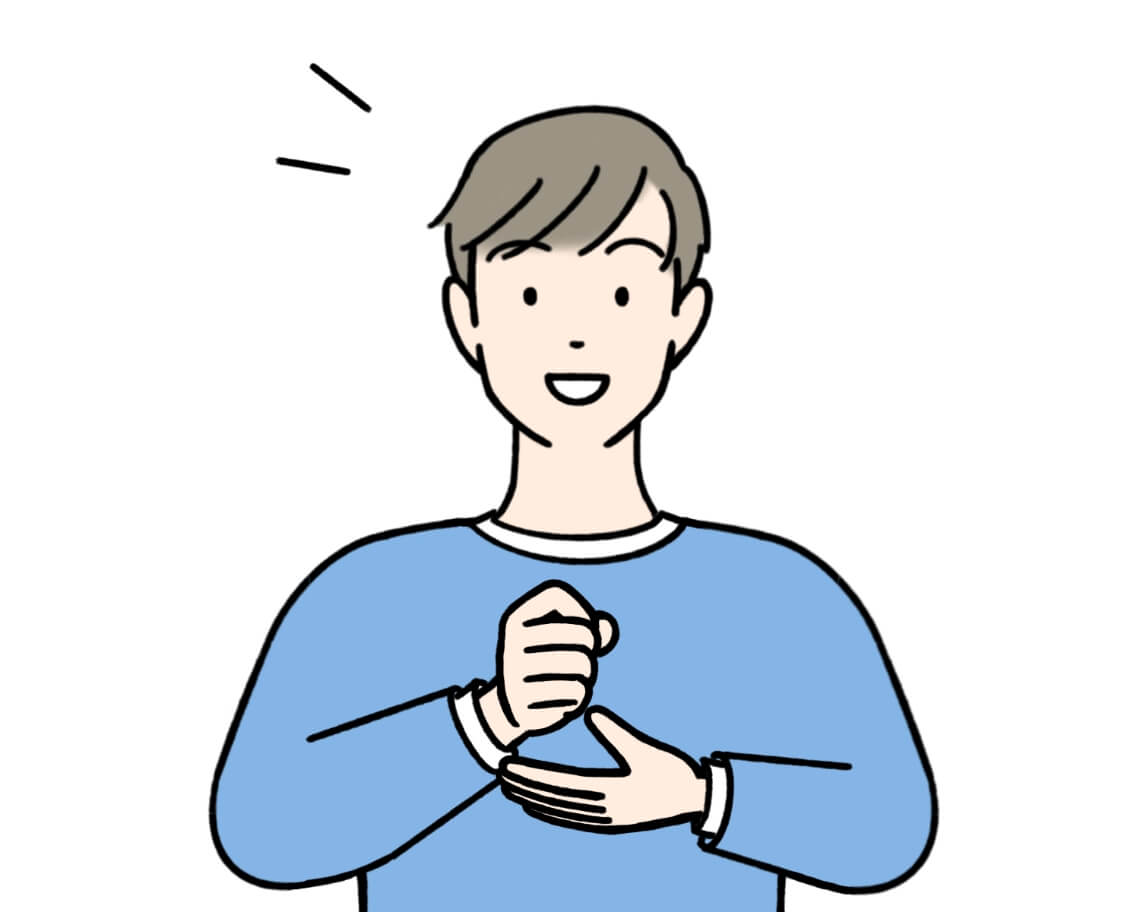
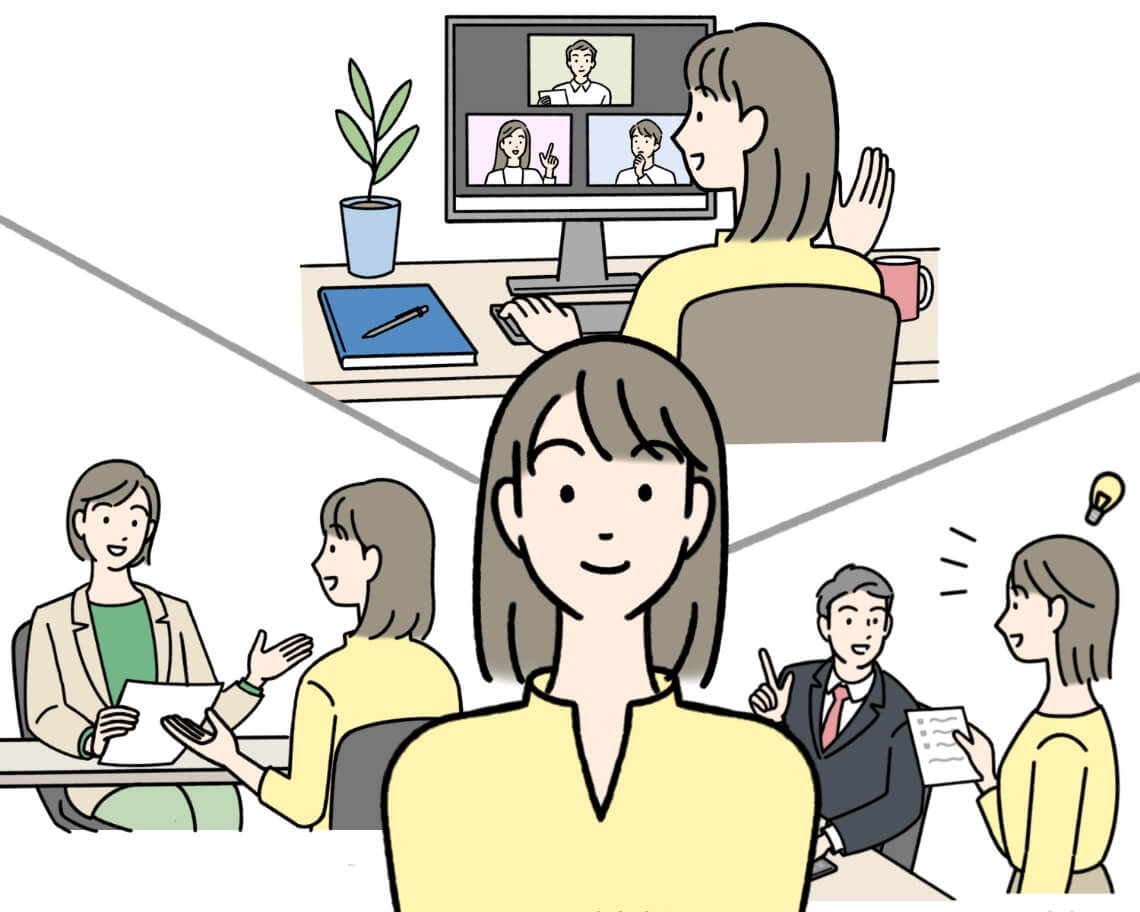
発達障害の特性に対処し、うまく付き合うには、それぞれの特性が日常生活に支障を与えないようにコントロールすることが必要です。
そのためには、まず自分の障害の特性について理解すること(自己理解)が重要です。
その上で、障害の特性に合った職場や働き方、生活環境を選び、さらに周囲の人にサポートしてもらえるよう調整すること(環境調整)が重要になってきます。
また、特性があっても日常生活に支障がなければ、そのまま生活を続けることができます。
さらに、特性からくるストレス等により二次障害を発症している場合は、その症状に対して治療を行います。
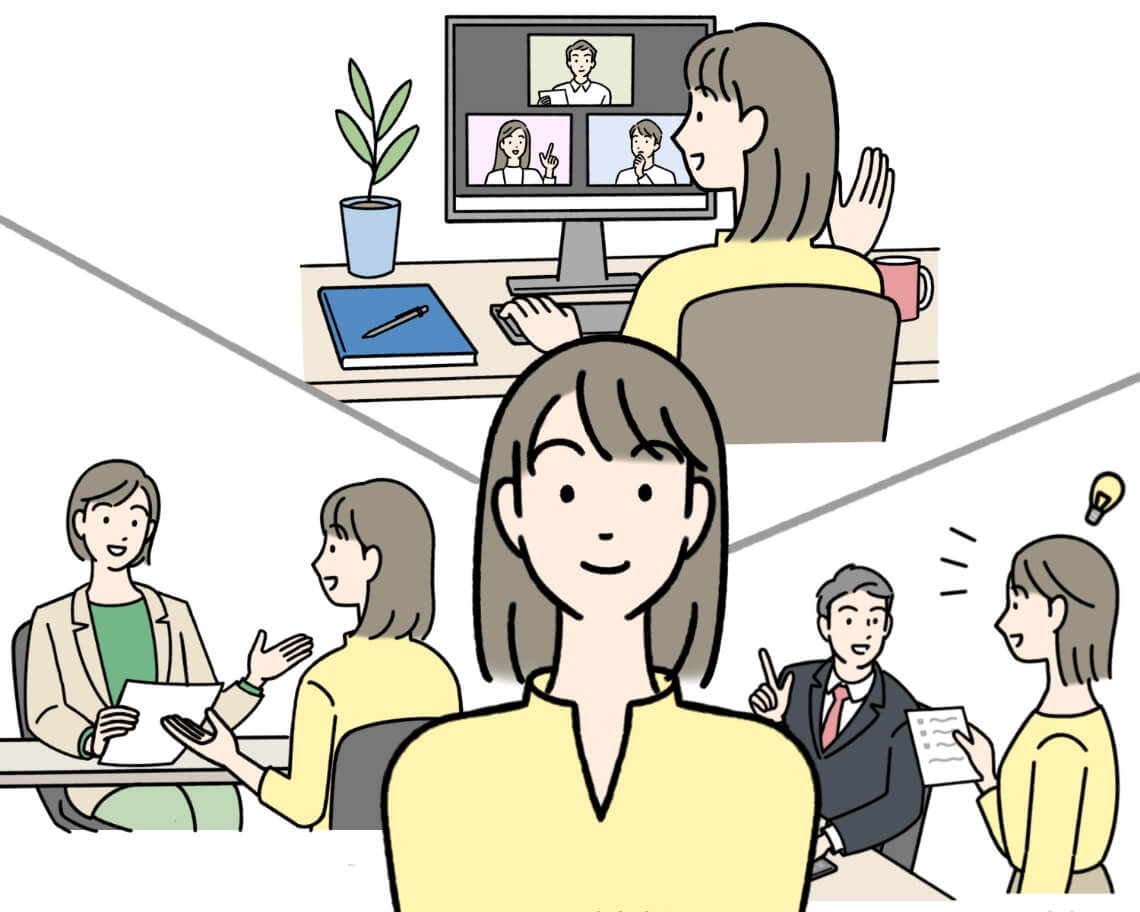
その上で、障害の特性に合った職場や働き方、生活環境を選び、さらに周囲の人にサポートしてもらえるよう調整すること(環境調整)が重要になってきます。
また、特性があっても日常生活に支障がなければ、そのまま生活を続けることができます。
さらに、特性からくるストレス等により二次障害を発症している場合は、その症状に対して治療を行います。
いろいろな対処法
日常生活に支障が出てしまう特性をやわらげたり、うまく付き合っていくためには、次のような方法があります。
それぞれの方法は正確な診断を元に医師と相談し、本人が納得し、承諾した上で進められます。また、いくつかの方法を並行して行うこともあります。もし、望まない方法や、不安なこと、疑問などがあれば、気軽に医師に相談してみましょう。
カウンセリング
医師もしくは臨床心理士と時間をかけて対話することで、自己理解を深めたり、特性への対処法について一緒に考えたり、職場などの環境へ適応できるようにしていきます。
リハビリテーションプログラム
同じ特性や困りごとを持つ人が集まり話し合いながら、自己理解を深めたり、コミュニケーション方法を学んだりする方法です。
認知行動療法
心理療法(カウンセリング)の技法のひとつで、バランスの取れた考え方を取れるようになることでストレスにうまく対応できるようにするものです。現実に起こっている問題に対する考え方や行動の偏りを少しずつ変えていくことで、特性とうまく付き合う方法を見つけることができます。
薬物療法
注意欠如多動症(ADHD)に対しては有効な薬があります。
自閉スペクトラム症(ASD)に対しても、二次的な精神症状に薬を使うことがあります。
環境調整
特性があっても周囲と上手く折り合えるよう、環境を調整することです。周囲の人に特性について相談したり、配慮をお願いしたり、仕事上での工夫を取り入れたりすることなどがあります。
環境調整のために、各種支援機関を活用することもできます。
各種福祉サービス、支援の利用
発達障害の特性により日常生活に困難がある場合、精神保健福祉士(ケースワーカー)などより、各種福祉サービスや支援について相談することができます。
注意欠如多動症(ADHD)への対処法
ADHDの特性による困りごとは、環境調整や薬物療法などで対処できる
発達障害はいわゆる「病気」ではなく「脳の特性」であることから、特性や困りごとへの対応方法についても「治療」ではなく「対処」と表現するのが望ましいでしょう。
ADHDの特性による困りごとや生きづらさを軽減する方法として、以下のような対処法があります。
環境調整、ソーシャルスキルトレーニングなどによる対処
ADHDと診断された場合、まず医師や臨床心理士などからのアドバイスをもとに集中しやすい環境をつくる「環境調整」や、日常生活で実際に遭遇するトラブルを回避するため、あいさつの仕方やメモの取り方などを具体的なロールプレイを通して学ぶ認知行動療法のひとつである「ソーシャルスキルトレーニング(SST)」などが行われます。
薬による対処
環境調整などの対処を行ってもADHDの症状の改善が十分ではない場合は、ADHDの症状を改善するための薬を使用することもあります。その際には、「通院日や通院時間を忘れがち」といった特性も考慮し、スマートフォンのスケジュール管理アプリの利用や、家族に通院情報を共有してリマインドしてもらうなどの工夫をするとよいでしょう。
薬は有効性と安全性のバランスに注意しながら選択されます。なお、薬を使う場合でも環境調整やSSTなども続けて取り組んでいくようにします。また、うつや不安などの精神的な不調を伴う場合には、その治療もあわせて行います。
そのほかにも、ADHDの症状によって日常生活に支障が出る場合は、ライフステージに応じてさまざまなサポートを受けることができます。
ひとりで悩まず、相談窓口や医療機関に相談することで、生きづらさを和らげることができるかもしれません。

自閉スペクトラム症(ASD)への対処法
ASDの特性によって生じる困りごとは、
ソーシャルスキルトレーニングなどで対処できる
ASDの特性による困りごとや生きづらさを軽減する方法として、以下のような対処法があります。
ソーシャルスキルトレーニングなどによる対処
社会的コミュニケーションに対する特性・障害に関しては、具体的な行動をロールプレイで学ぶ認知行動療法のひとつである「ソーシャルスキルトレーニング(SST)」や、個別のカウンセリングなどが行われます。
SSTの技法を発展させた、成人ASDに対するショートケア(デイケア)プログラムを実施している医療機関もあります。プログラムを実施している医療機関については、成人期発達障害支援学会のホームページをご参照ください。
薬による対処
イライラや不機嫌などの易刺激性(いしげきせい)、かんしゃくや多動、こだわりなどに対しては、薬によって軽減できる場合があります。また、二次的に引き起こされる抑うつ状態や不安などに対しても薬物治療を行うことがあります。
ASDで現れる特性によって日常生活に支障が出る場合は、ライフステージに応じてさまざまなサポートを受けることができます。
ひとりで悩まず、相談窓口や医療機関に相談することで、生きづらさを和らげることができるかもしれません。
限局性学習症(SLD)への対処法
SLDには特性に応じた周囲のサポートが大切
SLDの特性による困りごとや生きづらさを軽減する方法として、以下のような対処法があります。
ICT技術の活用
学童期のディスクレシアにおいては、解読指導アプリなどを用いて音読のつらさを軽減する方法を行うことがあります。
また、スマートフォンやタブレットで文字を拡大・音読するといった、ICT(Information and Communication Technology)技術の活用によるサポートも登場しています。
カウンセリングや環境調整
SLDの特性を持つ人には、周囲のサポートが重要です。基本的には家庭や職場の環境を整え、適切なカウンセリングを行うことなどによって、読み書きや計算などで生じる困りごとを軽減する方法がとられます。
たとえば職場では、読みにくさを軽減するためにマーカーなどを使って大事なポイントを強調したり、指示をメモしたりメールで送ったりするなどの方法が考えられます。

たとえば職場では、読みにくさを軽減するためにマーカーなどを使って大事なポイントを強調したり、指示をメモしたりメールで送ったりするなどの方法が考えられます。
また、うつ病や不安症、睡眠・覚醒障害などの精神的な疾患を合併する場合(二次障害)は、それぞれ抗うつ剤や抗不安剤、睡眠導入剤などの薬を用いた治療も行います。
いまメンタルヘルスで苦しんでいる方へ
-ご自身の特性に、一度目を向けてみませんか?
自分の特性を知って対処することで、うつ症状などといった二次障害のコントロールにつながることもあります。
<経験者の声>
発達障害への対処が二次障害のコントロールにつながったという経験者の声を集めました。
過去にADHD診断済みであったが、仕事内容が合わずうつ症状を発症したAさん
また、職業検査(GATB)や自己分析の結果、言葉を扱うことや、初対面の人と物怖じせず接し、じっくりお話を聞きながら対人関係を築くことが得意だと分かりました。現在は得意を活かした仕事をしています。
自分で自分の特性を理解することは必須だと思います。うつ発症時は、自分の「苦手」ばかりに目が向いていましたが、思い切って周りの方に「自分の長所」を聞いてみることも参考になりますし、元気が出ると思います。
うつ症状が長期間続いているなら、自分の特性を棚卸する時間を設けてみてください。
自分の特性を認知できておらず、自分の努力不足だと考え、うつ症状を発症したBさん
最近、勇気を出して職場にも特性について説明しました。周囲は長所も短所も受け入れてくれ、仕事の依頼方法等も工夫してくれています。周囲とコミュニケーションの工夫を共有することで、お互いにフラストレーションがたまりにくくなりました。上司はプラス面もしっかり評価してくれています。今では失敗した時、多少落ち込んでも立ち直ることができますし、自分を否定することも減り、うつ症状は生じにくくなっています。
監修:昭和大学 発達障害医療研究所
所長(准教授) 太田晴久先生
本文中に使用されている専門用語(アンダーラインのついたもの)については発達障害関連ワード集に詳しく説明があります。

